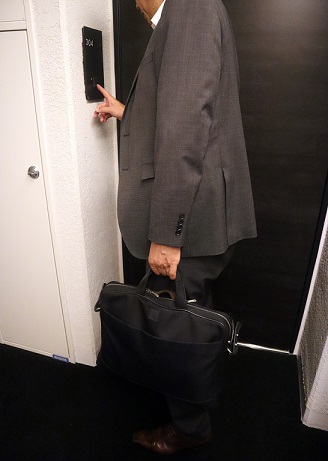2020年3月– date –
-

貴金属売却にまつわる税金知識
近時、金相場高騰に伴い貴金属を売却されるお客様が多数いらっしゃいますが、同時に税金面に関しても疑問を持たれる方もいらっしゃいます。そこで、「貴金属売却にまつわる税金知識」と題しまして貴金属売却の際に発生すると想定される税金のポイントをま... -

出張買取:理論編
【クーリングオフの適用】 買取をする際にクーリングオフが適用されるのは、どんな場合ですか? 出張買取や訪問買取の場合、 売主が売買の申込書や契約書を受け取った日から8日以内は、売主は商品の返却要求ができます。これは、いわゆる押し買い業者によ... -

ご依頼から古物商許可証取得までの流れ
こちらのサイトで古物商の許可申請をお願いしようと思うのですが、どうしたらいいですか? ありがとうございます。ご依頼から古物商許可証の取得までの流れをまとめましたのでご覧ください。それでも不明な点があればメールフォームや電話でご質問を承りま...
1